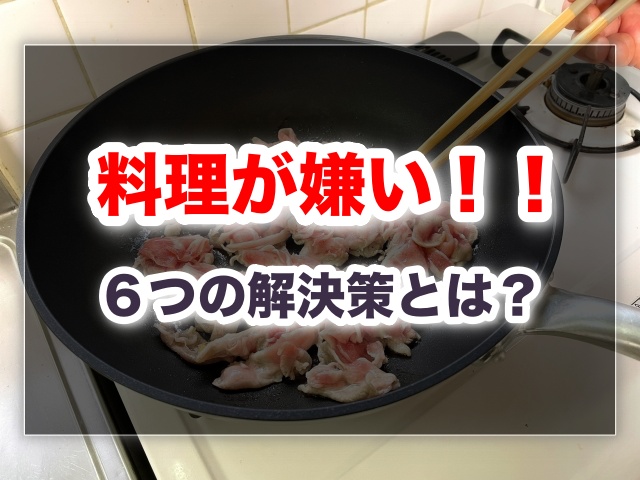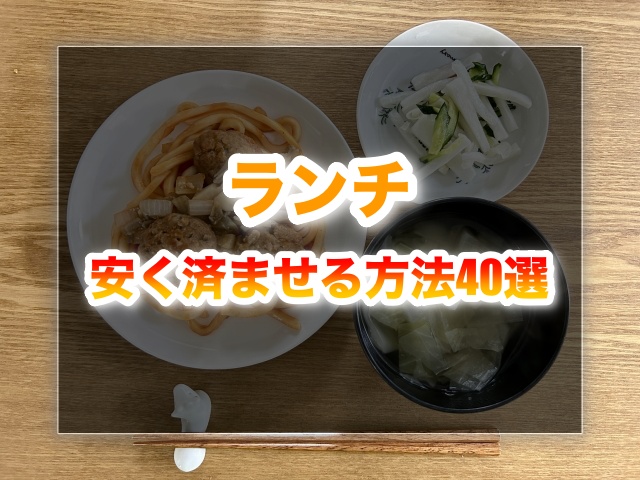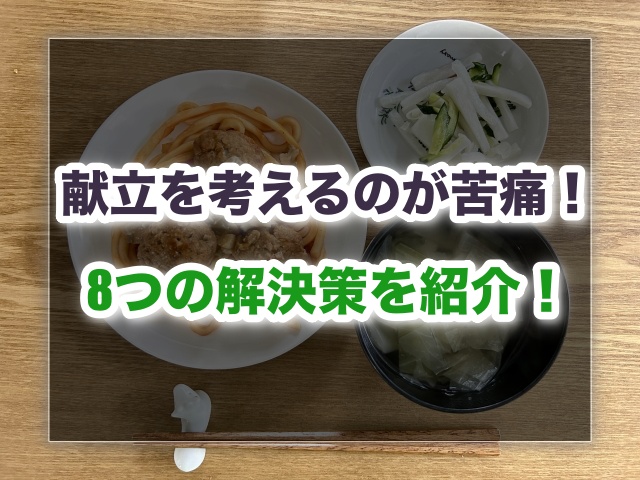Uber Eatsや出前館が高い!解決策を10個考えてみた!

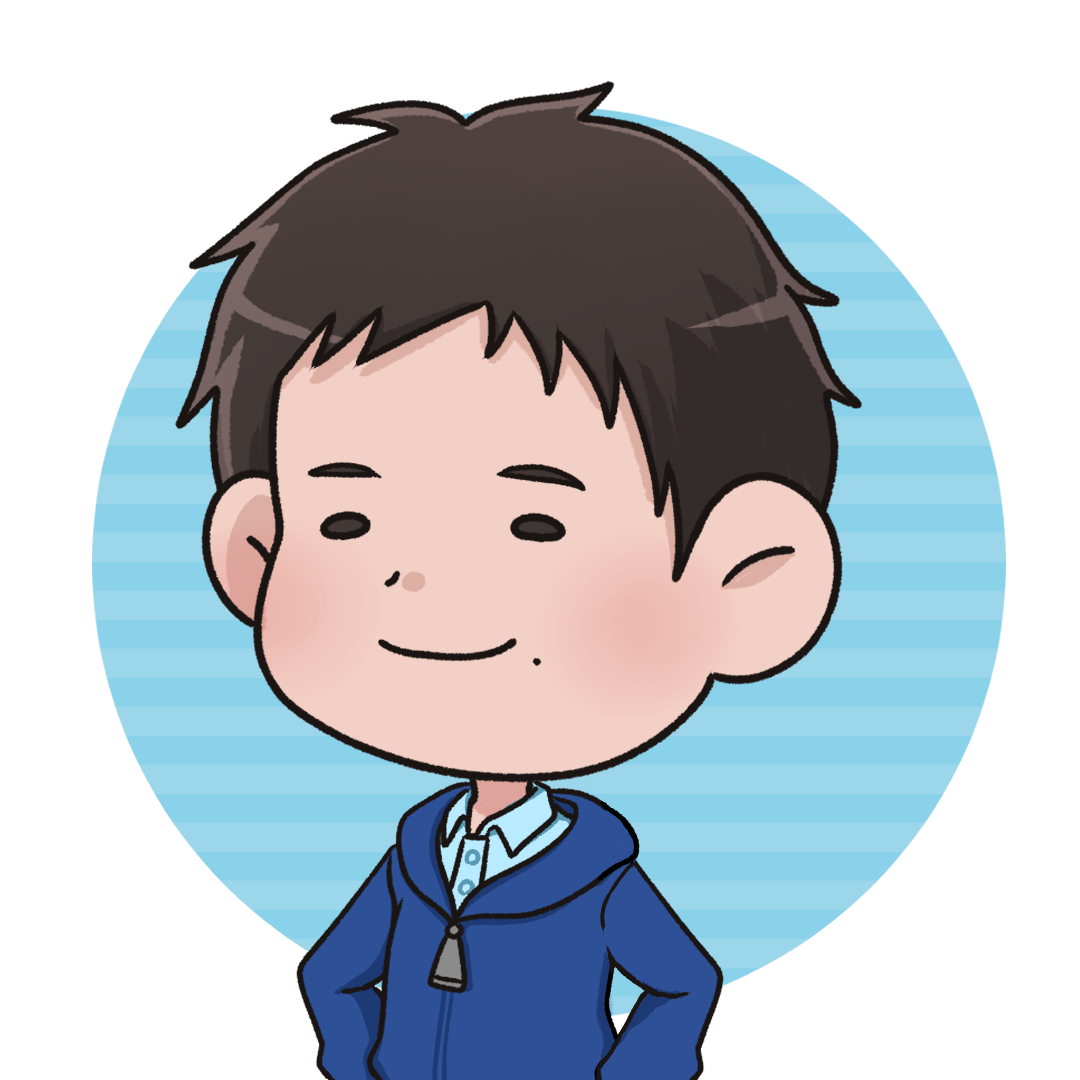
どうもりょうです。
Uber Eats とか出前館って便利ですが、料金が高いですよね・・・
しょっちゅう使っていると金欠になります。マジで。
ということで、その解決策を10個考えてみました。
なぜこんなに高いの?デリバリー料金の内訳

フードデリバリーサービスを利用すると、思った以上に高額になってしまう経験はありませんか?
その理由を理解することが、節約の第一歩です。
主な費用項目
- 商品代金(店舗価格より高く設定されることが多い)
- 配送料(距離や時間帯により変動)
- サービス料(売上の一定割合)
- 少額注文手数料(最低注文金額を下回る場合)
- チップ(一部サービス)
これらが積み重なると、1回の注文で数百円から千円以上の追加費用が発生することも珍しくありません。
【即効性あり】今すぐできる節約術
1. 複数のアプリを使い分ける
各プラットフォームで料金体系が異なるため、同じ店舗でも価格差が生じます。注文前に必ず比較しましょう。ちょっと面倒ですが。。。
主要アプリの特徴
- Uber Eats: 配送エリアが広く、プロモーション頻度が高い
- 出前館: 配送料が比較的安く、セール時の割引率が大きい
- foodpanda: 定期的な無料配送キャンペーン
- Wolt: 高品質な店舗が多く、サービス料が明確
2. プロモーションコードを活用する
各サービスのアプリ内や公式SNSで頻繁に配布されるクーポンを見逃さないようにしましょう。
効果的なクーポン活用法
- 初回利用者向けの大幅割引クーポン
- 雨の日限定クーポン
- 特定時間帯の配送料無料クーポン
- 友達紹介キャンペーン
3. 月額プランを検討する
頻繁に利用する場合は、月額プランが結果的にお得になることがあります。
各サービスの月額プラン例
- Uber Eats: Uber One(月額498円)→配送料無料
- 出前館: 出前館プレミアム(月額330円)→配送料割引
【根本解決】デリバリー費用を抑える生活習慣
4. まとめ注文で単価を下げる
1回の注文金額を増やすことで、相対的に追加費用の負担を軽減できます。
まとめ注文のコツ
- 冷凍・冷蔵保存できるメニューを選ぶ
- 職場や友人とのシェア注文
- 翌日の分も含めて注文
- 最低注文金額を満たす商品を戦略的に選択
5. 店舗の直接注文システムを利用する
多くの飲食店が独自の配送サービスや電話注文に対応しています。プラットフォーム手数料がかからない分、安価な場合があります。
6. 時間帯と天候を意識する
需要が高い時間帯や悪天候時は配送料が高くなる傾向があります。
料金が安くなりやすい時間帯
- 平日の14時〜17時
- 深夜帯(対応店舗は限定)
- 晴れた日の通常時間
【代替手段】デリバリー以外の選択肢
7. テイクアウトサービスの活用
自分で取りに行くことで配送料を完全に削減できます。
テイクアウトのメリット
- 配送料・サービス料が不要
- 待ち時間が予測しやすい
- 店舗限定のテイクアウト割引がある場合も
8. 冷凍食品の活用
技術の進歩により、デリバリー並みの美味しさの冷凍食品が増えています。
コスパ優秀な冷凍食品例
- 冷凍ピザ(1枚200円〜400円)
- 冷凍パスタ(1人前150円〜300円)
- 冷凍弁当(1食300円〜500円)
9. 宅配弁当サービスの活用

デリバリーと食材配達の中間的な選択肢として、宅配弁当サービスが注目されています。
主要な宅配弁当サービス
nosh(ナッシュ)
- 料金:1食499円〜(送料別途913円〜)
- 特徴:糖質30g以下、塩分2.5g以下の健康重視メニュー
- メリット:栄養管理されている、メニューが豊富(60種類以上)

ワタミの宅食
- 料金:1食490円〜(送料無料)
- 特徴:高齢者向けから働く世代まで幅広いメニュー
- メリット:送料無料、栄養バランスが良い
ヨシケイ
- 料金:1食300円〜(送料無料)
- 特徴:食材とレシピがセットで届く
- メリット:自分で調理する楽しみ、食材の無駄がない
冷凍弁当宅配(まごころケア食など)
- 料金:1食470円〜(送料込み)
- 特徴:冷凍で長期保存可能、レンジで温めるだけ
- メリット:まとめ買いで単価DOWN、保存が利く
宅配弁当 vs デリバリーサービス比較
| 項目 | 宅配弁当 | デリバリーサービス |
|---|---|---|
| 1食あたり価格 | 300円〜700円 | 1,200円〜2,500円 |
| 栄養バランス | 管理栄養士監修 | 店舗により差が大きい |
| 配送頻度 | 週1回まとめ配送 | 注文の都度配送 |
| 保存期間 | 冷凍で1ヶ月程度 | 当日消費 |
| 調理時間 | 電子レンジ3〜5分 | 調理不要 |
宅配弁当活用のメリット
- 圧倒的なコスパ:デリバリーの1/3〜1/2の価格
- 栄養管理:管理栄養士監修で健康的
- 時短効果:電子レンジで温めるだけ
- 計画的な食事:まとめ配送で衝動的な注文を防げる
効果的な利用パターン
- 平日ランチ用:在宅勤務時の昼食として
- 夕食の一部:メインディッシュとして、副菜は自作
- 忙しい週の備蓄:冷凍庫にストックして緊急時に活用
- ダイエット期間:カロリー計算済みで体重管理
10. 食材配達サービスの併用
食材を配達してもらい、簡単な調理で済ませる方法も効果的です。
主要な食材配達サービスの特徴
Amazonフレッシュ・ライフ
- 配送料:390円〜(プライム会員は一定額以上で無料)
- 特徴:生鮮食品から日用品まで幅広い品揃え
- メリット:当日・翌日配送、品質が安定している
イオンネットスーパー
- 配送料:330円〜(地域により異なる)
- 特徴:店舗と同じ価格設定、プライベートブランド商品が豊富
- メリット:置き配対応、まとめ買い割引
楽天西友ネットスーパー
- 配送料:330円〜(楽天会員は一定額以上で無料)
- 特徴:低価格帯商品が充実、楽天ポイントが貯まる
- メリット:コスパが良い、ポイント還元でさらにお得
コープの宅配(生協)
- 配送料:200円〜(利用頻度により変動)
- 特徴:安全性にこだわった商品、冷凍食品が充実
- メリット:定期利用で配送料割引、品質への信頼度が高い
食材配達を活用した節約レシピ例
10分で完成!簡単パスタ
- 材料費:約300円/人
- 冷凍野菜ミックス + パスタ + 市販ソース
- デリバリーピザ(1,500円)と比較して約1,200円の節約
レンジで作る丼もの
- 材料費:約400円/人
- 冷凍ご飯 + 冷凍から揚げ + 野菜 + 調味料
- デリバリー弁当(1,800円)と比較して約1,400円の節約
栄養バランス重視の炒め物
- 材料費:約350円/人
- 冷凍野菜 + 肉類 + 調味料
- デリバリー中華(2,000円)と比較して約1,650円の節約
食材配達サービス活用のコツ
- 定期利用でコストダウン
- 週1回程度の定期利用で配送料を抑制
- まとめ買いによる単価削減効果
- 冷凍食品の戦略的活用
- 冷凍野菜で栄養バランスを確保
- 冷凍肉・魚で調理時間を短縮
- 冷凍ご飯で炭水化物を手軽に摂取
- 調理時間を最小限に
- 電子レンジ調理可能な商品を選択
- カット野菜や下処理済み商品を活用
- 調味料は万能タイプを常備
月間コスト比較(週2回利用の場合)
- デリバリー利用:約16,000円/月
- 食材配達 + 簡単調理:約8,000円/月
- 月間節約額:約8,000円
食材配達サービスのデメリットと対策
デメリット
- 送料がかかる(330円〜500円程度)
- 最低注文金額の設定がある場合
- 配送時間に制約がある
対策
- 日用品もまとめて注文して送料を相殺
- 冷凍・冷蔵品をストックして計画的に利用
- 複数サービスの送料無料条件を把握して使い分け
【計算してみよう】月間デリバリー費用の見える化
自分の利用パターンを把握することで、より効果的な節約戦略を立てられます。
月間費用計算の例
- 週2回利用 × 月4週 = 月8回
- 1回あたり平均2,000円(追加費用含む)
- 月間総額:16,000円
- 年間総額:192,000円
この金額を見ると、節約の必要性が実感できるのではないでしょうか。
まとめ:バランスの取れたデリバリー活用術
デリバリーサービスは便利な反面、頻繁に利用すると家計を圧迫します。しかし、完全に利用を止める必要はありません。
効果的な活用方針
- 週に1〜2回程度に利用頻度を制限
- 利用時は必ずクーポンやプロモーションを確認
- 複数アプリで価格比較を習慣化
- 特別な日や忙しい時の「ご褒美」として位置づける
賢く利用することで、便利さを保ちながら節約も実現できます。今日から実践して、食費の見直しを始めてみませんか?
この記事があなたの節約生活の参考になれば幸いです。他にも家計管理のコツがあれば、ぜひコメントで教えてください!